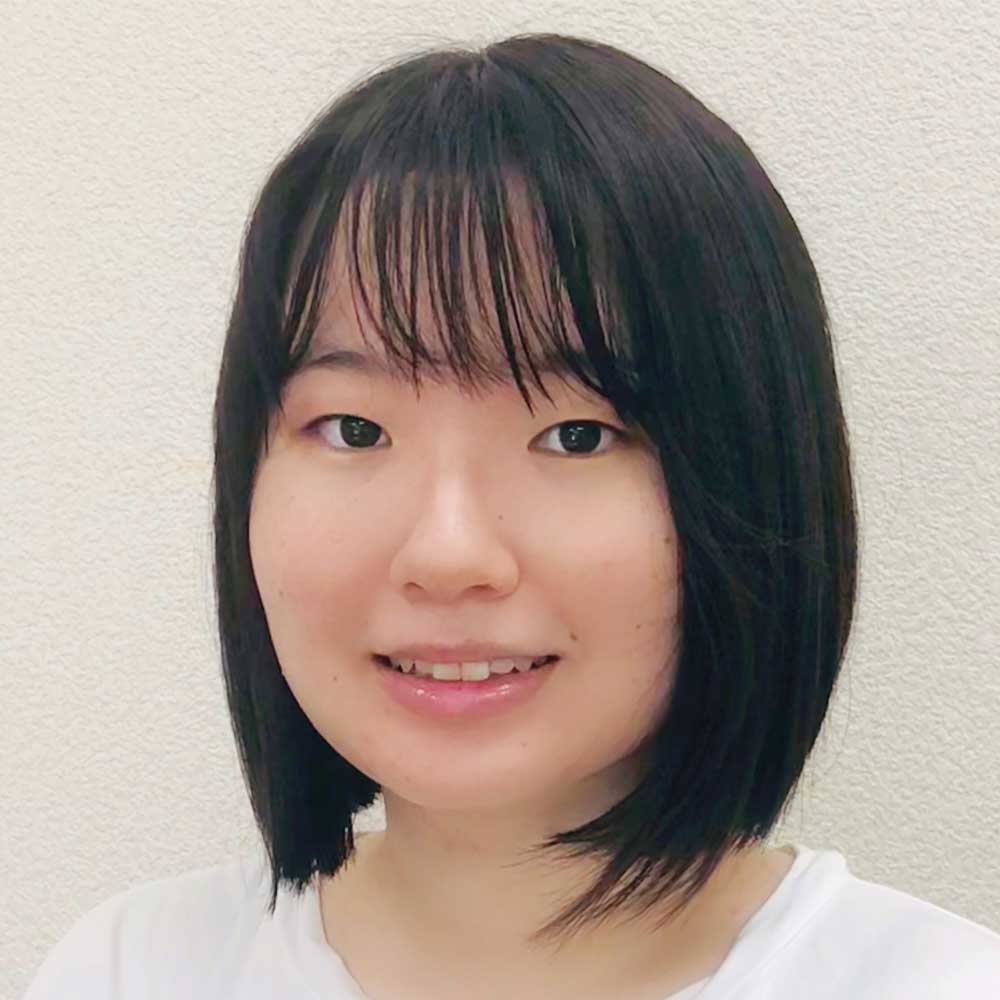
法学部町田 晴香MACHIDA Haruka
皆さんは法律というと、どんなことを思い浮かべますか。おそらく民法や刑法などのいわゆる六法をまずイメージするのではないでしょうか。
しかし、六法のみではなく、特別法などの細々とした法律はたくさんあります。
その中でも行政法は、「行政法」という個別の法律がある訳ではなく、簡単に言えば、行政に関わる法律を総称したものです。
行政法の判例は公(国や自治体)と私人の対立をを指します。
例えば、東日本大震災の後に、震災の補償として建物の倒壊の程度によって被災者生活再建支援金が支払われました。しかし、その倒壊の程度を決める審査に不備があったことによる裁判が行われました。間違えた審査の結果によって支援金が過剰に支払われてしまったのです。
このような事態は国民に対しての公平性に欠けてしまいます。
税金を使っているのだから、過剰に支払われたと発覚したらすぐに返金するべきだと考える方もいると思います。
ただ、その方法には問題もあります。それは被災者生活再建支援金の性質です。災害が起きた場合、人々は一刻も早く元の生活に戻るために資金を使います。支援金はその資金の足しとなるものになります。
今回の場合、住民の側に非はないので、尚更行政の誤りにより使ってしまった支援金を返してほしいと言われても、住民は「そんなの聞いてないよ」と思うでしょう。
これは今後人々が行政のサービスを信用しなくなる可能性があり、行政の信頼が損なわれてしまうという問題もあります。
このように複雑な事実関係と問題を考慮しつつ、法律に則って最適な判断を下すことの難しさを感じます。
ゼミでは判例の考え方、学説などの分析を行っています。一方的な講義形式ではなく、少人数の学生と先生を交えた双方向の学びの場となっています。
学生が判例を調べ、発表していく形をとり、論点について議論を深めて、その判例の意義を探っていきます。このような説明では難しいと思うかもしれませんが、自分の気づいたことや疑問に思ったことを述べると、それが他の人の気づきになることもあり、議論を進むことも多いです。また、他の人の意見を聞くことで今までに得られなかった多角的な視野を持つこともできます。もちろん、何かわからないことがあれば、豊富な専門知識を持っている先生がわかりやすい解説と、新たな問題提起によって更なる学びへと繋がります。
日々の生活の中で法律を意識することはあまりないと思います。私は「赤信号は渡ってはいけない」という法律があるのは知っていましたが、その法律の条文を見たのは法学部に入ってからでした。
法律は私たちの暮らしている社会のルールのようなものです。堅苦しい文言もありますが、法学を知っておくことに損はないと思います。ぜひ皆さんも学んでみませんか。
2022年パンフレット掲載予定